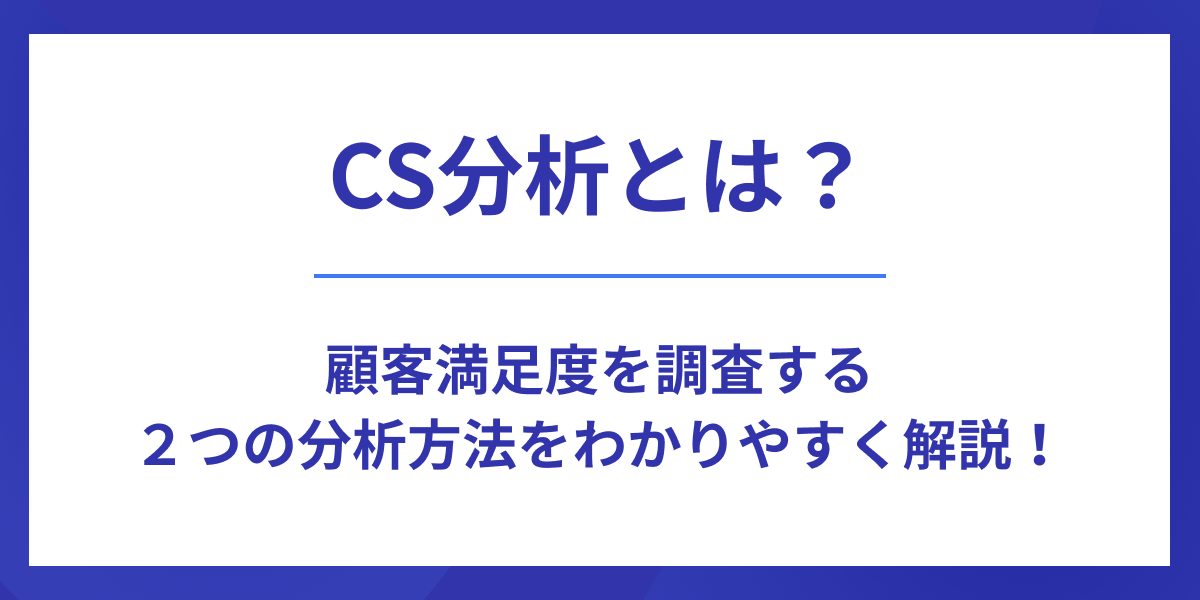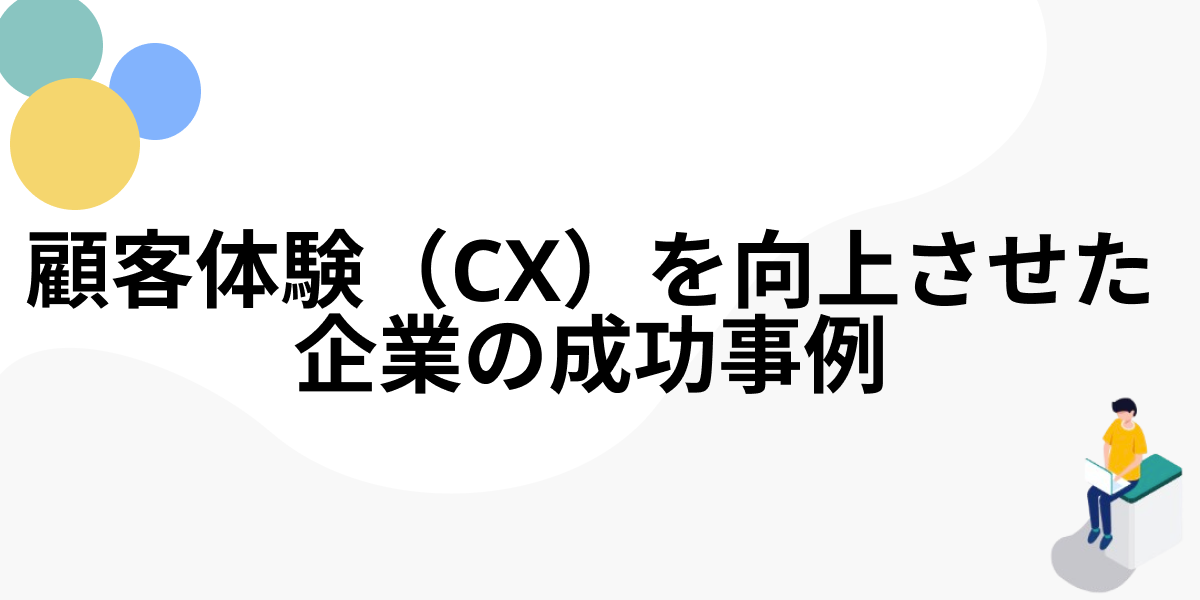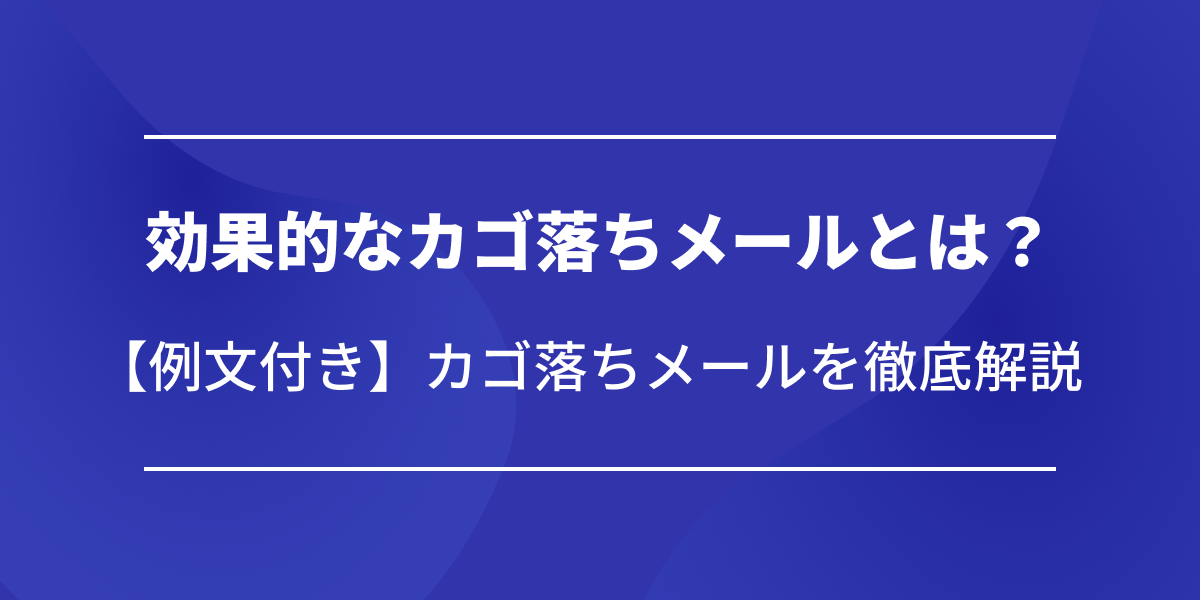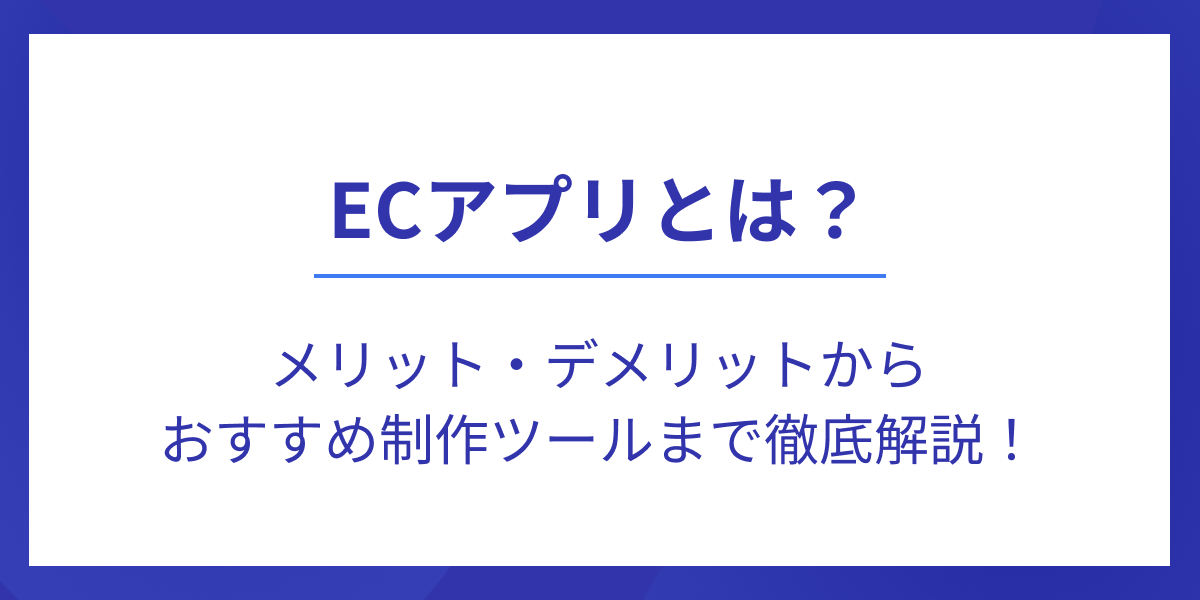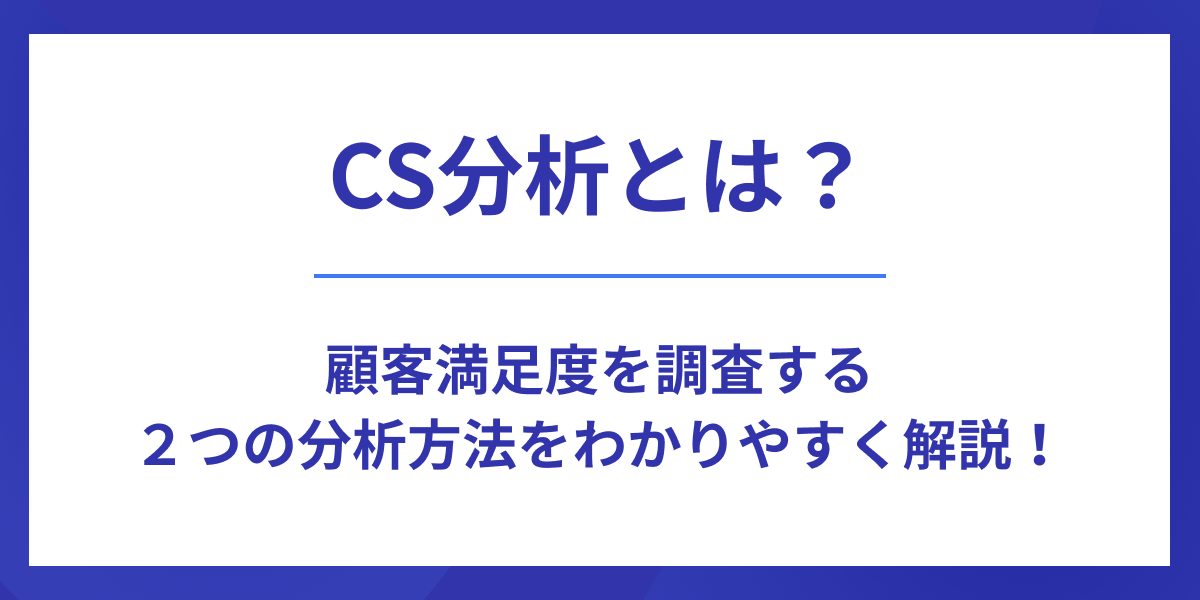
売上を維持し拡大していくためには商品やサービスの改善を図り、不足している部分を補ってお客様の満足度を高いレベルに保ち続ける必要があります。
限られたリソースや予算の中から商品やサービスの改善を行うに当たってはお客様の満足度を高めるポイントを見極めて実施していくことが重要です。
お客様の満足度を効果的に高められるポイントを見極める1つの手法としてCS(顧客満足度)分析があります。
商品や企業規模など問わずに顧客満足度調査は売上維持とアップには有効な手段です。
そこで今回の記事では、CS分析の概要から手法について解説します。
「リピーターが増えないので顧客満足度分析を行って改善したい」
「顧客満足度調査を行うが分析方法について知りたい」
「NPS計測とCS分析の違いを知りたい」
などとお考えの方に必見の記事です。
CS分析とは?

CSとはCustomer Satisfactionの略で、顧客満足度を意味しています。
この顧客満足度を分析するCS分析について説明します。
顧客満足度の必要性
顧客満足度とは企業や組織が提供している商品・サービスについて、お客様がどの程度満足しているかを数字で表したものです。
お客様が感じている満足度は主観的なもであり、企業は「顧客が自社商品・サービスに対してどれほど満足しているか」を判断することができません。しかし、その満足度をアンケートなどの調査によって数値化することによって商品やサービスに対する満足度を可視化することが可能となります。
同じような商品やサービスが多数の企業から提供される現代では、お客様の満足度を確実に把握する必要性があります。
お客様の満足度を把握した上で、お客様が満足に感じている部分は維持し伸ばし、不満に感じている部分は改善していくことが重要です。
CS分析とは
CS分析とはお客様が感じている満足度を項目別に的確に把握し、改善するべき項目の優先度を明らかにすることです。
CS分析を行うことにより満足度の低い項目の中から、さらに改善の優先度の高い項目を見つけることができます。
限られたリソースの中で抽出された項目を闇雲に対策していくのは得策ではありません。
優先順位を付けて売上アップが期待出来る項目から対策していく必要があります。
CS分析結果の活用事例
住宅メーカー
住宅を引き渡ししたお客様に満足度調査を実施しています。
月単位で調査結果を確認して、前月より評価が下がった営業拠点にヒアリングをしています。
基本的なことがきちんと行われているかの確認に使っています。
人材サービス業
課題のあぶり出しに利用しています。
たとえば前年度と比較してポイントの低かった「担当者の対応」について、課題認識して派遣スタッフとのより緊密なコミュニケーションを図れるように工夫を行いました。
NPS計測との違い

NPS計測とは?
NPSは「Net Promoter Score(ネットプロモータースコア)」の略で顧客ロイヤルティを測定する指標です。
NPSを計測するには以下のような質問を行いスコア集計します。
「あなたはこの商品(サービス)を友人や同僚にどれくらい薦めたいですか?」
という質問を行い0~10の11段階で評価してもらいます。
0~6を「批判者」、7と8を「中立者」、9と10を「推奨者」というカテゴリーに分けて、
「推奨者の割合(%)」-「批判者の割合(%)」を計算してNPSを導き出します。

NPS計測と顧客満足度の違い
NPSでは「あなたはこの商品(サービス)を友人や同僚にどれくらい薦めたいですか?」という質問に回答してもらうことから商品やサービスへのイメージを数値化したものと言えます。
また、「どれくらい薦めたいですか?」と質問することにより、将来的な行動も数値化していると言えます。
顧客満足度は購入者に「あなたは○○に満足していますか?」と質問することにより、現時点での商品やサービスへの評価を聞いていることになります。
言い換えると、NPSはお客様の商品やサービスに対する信頼や愛着などの感情を聞いているもので、顧客満足度は機能や価格などの合理的な理性で判断できる評価を聞いていることになります。
NPSと顧客満足度はどちらが優れている方式というものではなく、商品やサービスの売上維持やアップをするための両輪となるものです。
継続的に自社の商品やサービスを購入してもらうための課題を抽出するにはNPSが最適です。
商品やサービスを競合他社よりも優位に立つための課題を抽出するにはCS分析が最適です。
これらを踏まえた上で、目的に合わせてNPSかCS分析かを選択すると良いでしょう。
NPSについては、以下の記事にて詳細を説明しているので是非ご覧ください
▶︎NPS®とは?顧客満足度との違いから特徴や効果的な活用方法まで徹底解説
CS分析のやり方

顧客満足度調査の流れは以下のようになります。
1. 目的の明確化
顧客満足度調査で何を得たいかを明確にします。
例えば、製品の品質やサービス品質を定期的にモニタリングするための調査があります。
定点観測を行うことにより前回と比べて評価が低くなった項目に対して改善を行うことが可能です。
他には、新製品の売上げが期待したほどの金額でなかった場合に問題点を洗い出すための調査といった単発の調査があります。
目的によって調査の内容が変化しますので、明確化し内部で共有することが重要です。
2. 対象者の選定
新規顧客、リピーター客、年齢、性別など目的に応じた調査対象者を選定します。
3. 調査方法・体制・スケジュールの策定
目的や対象者に応じて、インターネット調査やインタビュー形式などを選定し、実行する体制やスケジュールを作成します。
4. アンケートの作成
目的に応じてアンケート内容を作成します。
顧客満足度アンケートの作り方については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
▶︎顧客満足度アンケートの作り方とは?重要ポイントからツールまで徹底解説!
5. CS分析
調査した結果を集計し分析を行います。
詳細についてはこの後の「クロス集計分析」と「ポートフォリオ分析」で解説します。
6. 課題の抽出
CS分析結果から課題形成を行います。
7. 改善策の策定と実行
課題を解決するための改善策を作成し実行していきます。
クロス集計分析
「クロス集計」とは質問と質問を掛け合わせて集計する方法です。
対比となる言葉として「単純集計」があります。「単純集計」は質問ごとに集計するやり方です。
「クロス集計」と「単純集計」について、具体的な例を挙げて説明します。
以下のようなアンケート調査があったとします。
Q1. あなたの性別を教えてください。
Q2. 商品Aのデザインには満足していますか?
- とても満足している
- 満足している
- どちらともいえない
- 満足していない
- まったく満足していない
■単純集計
回答者数:1,000人
Q1. あなたの性別を教えてください。
| |
人数
|
割合
|
|
男性
|
550
|
55%
|
|
女性
|
450
|
45%
|
Q2. 商品Aのデザインには満足していますか?
| |
人数
|
割合
|
|
とても満足している
|
200
|
20%
|
|
満足している
|
250
|
25%
|
|
どちらともいえない
|
300
|
30%
|
|
満足していない
|
150
|
15%
|
|
まったく満足していない
|
100
|
10%
|
■クロス集計
Q1. あなたの性別を教えてください。× Q2. 商品Aのデザインには満足していますか?
|
上段:人数
下段:割合
|
全体
|
とても満足している
|
満足している
|
どちらともいえない
|
満足していない
|
まったく満足していない
|
|
全体
|
1000
100%
|
200
20%
|
250
25%
|
300
30%
|
150
15%
|
100
10%
|
|
男性
|
550
100%
|
150
27%
|
200
36%
|
100
18%
|
50
9%
|
50
9%
|
|
女性
|
450
100%
|
50
11%
|
50
11%
|
200
44%
|
100
22%
|
50
11%
|
クロス集計を行うことにより、男女でデザインに対する満足度が違うことが浮き彫りになりました。
今回は性別という調査対象者の属性(性別、年齢、居住地、職業など)と属性以外の質問項目を掛け合わせましたが、属性以外の質問項目を掛け合わせることで、別の視点を得ることも可能になります。
ポートフォリオ分析
ポートフォリオ分析とは満足度と重要度の二つを縦横の軸として4分割した空間に各項目をマッピングしていくことで分析する手法です。
この手法は1970年代にボストン・コンサルティング・グループが開発したプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)をマーケティング用に応用したものです。

商品やサービスへの個別の項目に対する顧客の満足度と総合的な満足度を使って、個々の項目を上図の4象限にマッピングしていきます。
マッピングされた位置に従って、各項目への対策を決定していきます。
・項目のマッピング方法
顧客満足度調査では各質問への回答を以下のような5段階で求めます。
「とても満足している」「満足している」「どちらともいえない」「満足していない」「まったく満足していない」
また、総合的な満足度も質問に加えておきます。

得られた結果を上記のように表計算ソフトで集計を行います。
満足度は「とても満足している」と「満足している」を加算したもので、重要度は「総合満足度」と各質問の集計結果との相関係数で算出します。
つまり、「総合満足度」と相関が高い項目が総合満足度に影響を与えるものであり重要度が高いと言えます。
満足度と重要度で散布図を作成して、各項目を4象限にマッピングします。

それぞれの項目への対応方針については、項目がどの象限にプロットされているかにより違ってきます。
各象限の説明を以下に示します。
・重点維持項目
右上の象限は「重点維持項目」と呼ばれます。この象限は項目別の満足度は高く、「総合満足度」との相関が高いので今後とも維持し強化を図っていく必要があります。
上の図では「品質」が重点維持項目になります。
・維持項目
左上の象限は「維持項目」と呼ばれます。この象限は項目別の満足度は高く、「総合満足度」との相関は低いので現状維持で十分です。
上の図では「速度」が維持項目になります。
・改善項目
左下の象限は「改善項目」と呼ばれます。この象限は項目別の満足度は低く、「総合満足度」との相関は低いので、次に説明する重点改善項目の改善を行ったあとに対応すれば良く、優先度は低いと考えられます。
上の図では「デザイン」「操作性」「画面の大きさ」が改善項目になります。
重点改善項目
右下の象限は「重点改善項目」と呼ばれます。この象限は項目別の満足度は低く、「総合満足度」との相関は高いので、重点的に改善すべき項目で優先度は高いと考えられます。
上の図では「価格」「機能性」が重点改善項目になります。
まとめ

コストと時間をかけて収集した顧客満足度の調査結果を売上維持や拡大、新商品開発へつなぐためには正しく読み解くためのCS分析は必須のスキルです。
今回の記事を参考にしてクロス集計やポートフォリオ分析を利用して的確な改善点を発見するようにしてください。
また、顧客満足度調査は1回限りのものではなく繰り返し行っていくことで、自社ならではのノウハウや知見が蓄積していきますので今回の記事をスタート地点として実行して見てはいかがでしょうか。