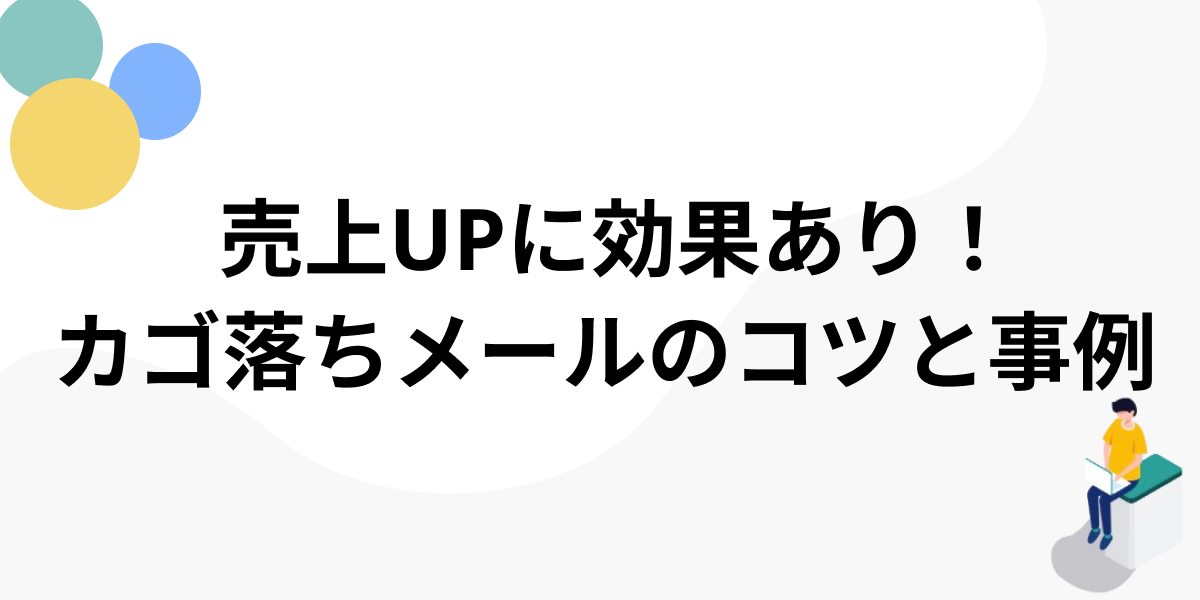ECサイトを運営していると、一度は耳にする「カゴ落ち(カート放棄)」。
これは、ユーザーが商品をカートに入れたにもかかわらず、最終的に購入に至らないまま離脱してしまう現象を指します。実際、多くのECサイトでは70%以上のユーザーがカゴ落ちしているとも言われており、放置すれば売上や顧客満足度に大きな損失をもたらします。
なぜユーザーは購入直前で離脱してしまうのでしょうか?
そして、どうすればその離脱を防ぎ、CVR(転換率)を改善できるのでしょうか?
本記事では、「カゴ落ちとは何か?」という基本から、発生する原因、具体的な対策方法、ツール活用、さらに成功事例までを徹底解説します。
ECサイトの売上改善に取り組むすべての方に役立つ実践的な内容をお届けします。

カゴ落ちとは?

カゴ落ちの定義(カート放棄)
「カゴ落ち」とは、ユーザーがECサイトで商品をカート(買い物かご)に追加したにもかかわらず、購入手続きに進まず、サイトを離れてしまう行動を指します。英語では「Shopping Cart Abandonment(ショッピングカート放棄)」とも呼ばれ、世界中のECサイトが直面する共通課題です。
「カートに入れたのに購入しない」状態とは
カートに商品を入れるという行動は、ユーザーが購買意欲を持っている証拠です。しかし、そのまま購入しないまま離脱するケースは非常に多く、一般的にカゴ落ち率は60〜80%にのぼるとされています。
ユーザーが「今は買わなくてもいいかな」「思っていたより送料が高い」「入力が面倒」と感じた瞬間に、購入プロセスから離脱してしまうのです。これは非常にもったいない機会損失であり、ECサイト運営者にとっては見過ごせない問題です。
ECサイト運営における重要な課題
カゴ落ちは、一見するとユーザーの気まぐれのように思えますが、実際にはサイト側の設計・情報提供・体験設計に原因があることも多いです。
たとえば、配送情報が分かりづらい、決済方法が少ない、セキュリティ面で不安を感じるなど、細かなストレスがユーザーの購買意欲を削いでいる可能性があります。
つまり、カゴ落ちは売上を伸ばすうえで最大の「取りこぼし」ポイント。ここを改善することで、広告費や集客施策を最大限に活かし、転換率(CVR)とLTV(顧客生涯価値)の向上につなげることができます。
次のセクションでは、カゴ落ち率の計算方法や、目安となる数値について解説します。どれくらいの割合でカゴ落ちが発生しているのかを知ることが、改善の第一歩です。
カゴ落ち率の計算方法

カゴ落ち率の算出式
「カゴ落ち率」は、カートに商品を追加したユーザーのうち、最終的に購入に至らなかった割合を示す指標です。計算式は以下の通りです。
カゴ落ち率(%)=(カート追加数 − 購入完了数)÷ カート追加数 × 100
たとえば
- カートに追加したユーザー:1,000人
- 実際に購入に至ったユーザー:300人
この場合のカゴ落ち率は
(1,000 − 300)÷ 1,000 × 100 = 70%
つまり、7割のユーザーが購入せずに離脱していることになります。
購入完了率との違い
カゴ落ち率と混同しやすいのが「購入完了率(CVR)」です。
それぞれの違いをまとめると以下の通りです。
|
指標名
|
対象母数
|
意味
|
|
カゴ落ち率
|
カート追加ユーザー
|
カートに入れたのに購入しなかった割合
|
|
購入完了率(CVR)
|
サイト訪問者全体
|
訪問者のうち購入に至った割合
|
つまり、カゴ落ち率は“あと一歩”で離脱してしまったユーザーの分析に役立ち、購入完了率はサイト全体のコンバージョン力を示す指標として活用されます。
カゴ落ち率の目安・平均値(業界別など)
カゴ落ちはどのECサイトにも起こるものですが、その割合には業種や商材、ターゲット層によって違いがあります。以下は一般的な業界別のカゴ落ち率の目安です。
|
業種・カテゴリ
|
平均カゴ落ち率の目安
|
|
アパレル・ファッション
|
65〜80%
|
|
家電・ガジェット
|
70〜85%
|
|
美容・コスメ
|
60〜75%
|
|
食品・日用品
|
55〜70%
|
|
高額商材(家具・旅行など)
|
80〜90%
|
このように、高単価の商品ほど比較・検討が長引き、カゴ落ち率も高くなる傾向があります。
「うちのサイトのカゴ落ち率は高すぎるのでは?」と感じたら、まずは業界平均と比較したうえで、自社の導線やフォーム設計に改善点がないかを見直してみましょう。
カゴ落ちが発生する主な原因

ユーザーが「商品をカートに入れたのに購入に至らない」理由は、単なる気まぐれではありません。多くの場合、購入直前での不安やストレスが原因となって離脱しているのです。ここでは、ECサイトにおいてよく見られるカゴ落ちの主な要因を解説します。
配送料・手数料が高い
購入手続きの途中で、思っていた以上の送料や決済手数料が加算されると、ユーザーは一気に購入意欲を失ってしまいます。
- 商品価格は安かったのに、送料で高額になる
- 送料無料ラインが高すぎる
- 手数料の記載が事前になかった
こうしたギャップは「不信感」や「割高感」につながり、カゴ落ちの大きな要因になります。
会員登録や入力フォームが面倒
購入前に強制的な会員登録を求められたり、入力項目が多すぎるフォームに直面したりすると、ユーザーは面倒に感じて離脱しやすくなります。
- メール認証の必要がある
- 住所や氏名の入力欄が細かすぎる
- パスワード要件が厳しすぎる
特にスマホユーザーにとっては、入力の手間=離脱のリスクと直結します。
到着日が遅い・配送条件が分かりづらい
「いつ届くか分からない」「希望日に間に合わない」といった不安があると、ユーザーは購入を控えます。
- 到着予定日の表示がない
- 配送方法が選べない
- 納期が長すぎる(例:5営業日後発送)
特にギフトや急ぎの購入ニーズでは、配送条件が曖昧なだけで即離脱される可能性が高まります。
決済手段が少ない
ユーザーが希望する決済方法が選べないと、購入を諦めるケースが少なくありません。
- クレジットカード以外の選択肢がない
- コンビニ払いや後払いが使えない
- スマホ決済・QRコード決済が非対応
最近では多様な決済ニーズに応えることが、購入完了率の向上に直結する要素になっています。
サイトが使いにくい/スマホ対応が不十分
せっかく商品を選んでも、サイトの操作性が悪いとスムーズに購入まで進めません。
- ボタンが小さくて押しづらい
- ページの読み込みが遅い
- スマホでレイアウトが崩れている
とくにモバイルユーザーの割合が高い現在、スマホ最適化が不十分なサイトはカゴ落ちのリスクが高まります。
セキュリティ・信頼性への不安
「このサイトで本当に買って大丈夫?」と少しでも思わせてしまった時点で、ユーザーは購入を躊躇します。
- 会社情報や運営者情報が掲載されていない
- SSL対応していない(URLが「http」のまま)
- レビューや実績がない/少ない
信頼性が感じられないサイトは、特に初回訪問者の離脱率が高くなる傾向にあります。
カゴ落ちがもたらすデメリット

「カートに入れたけど、購入に至らなかった」― この行動が積み重なることで、ECサイトの売上やブランド力に少なからぬ悪影響を与えます。
ここでは、カゴ落ちを放置することによって発生する3つの主なデメリットを解説します。
売上機会の損失
カゴ落ちは、「あと一歩で売上になるはずだったユーザー」を失う行動です。
商品をカートに入れる段階まで来ているということは、購入意欲が高いユーザーです。そのような見込み客が離脱してしまうのは、極めて大きな機会損失です。
たとえば
- 月間1万件のカート追加があっても、カゴ落ち率が70%なら、7,000件の購入機会を逃していることになります。
放置しておけば、それだけ本来得られたはずの利益が流出している状態となります。
広告費の無駄(獲得単価の悪化)
集客に広告を活用している場合、カゴ落ちは広告費用対効果(ROAS)やCPA(顧客獲得単価)を大きく悪化させる要因になります。
- 広告で誘導したユーザーがカートまで進んでも、購入されなければ投資が無駄に終わる
- カゴ落ちが多いと、CPAが上昇し、全体のマーケティング効率が低下する
せっかくの広告費も、カゴ落ちを防げなければ“穴のあいたバケツ”に水を注いでいるような状態になってしまいます。
顧客体験の悪化・ブランドイメージ低下
購入途中で離脱されたということは、ユーザーが「使いにくい」「不安がある」「魅力が伝わらない」と感じた可能性が高いということです。
これは顧客体験(CX)の低下につながり、結果としてブランド全体の印象や信頼性にまで悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 使いづらいフォームや決済で「もう使いたくない」と思われる
- 送料や条件がわかりづらく「不親切なサイト」と感じられる
- 離脱後に口コミやSNSでネガティブな印象を発信される可能性も
カゴ落ち=目に見えない“不満のサイン”ともいえるため、早期に対応することで顧客ロイヤルティの低下を防ぐことができます。
カゴ落ちを防ぐ対策・改善方法

カゴ落ちはECサイトにおける大きな機会損失ですが、適切な対策を講じることで、コンバージョン率の向上とLTVの最大化が見込めます。ここでは、特に効果の高いカゴ落ち対策を6つ紹介します。
フォームの最適化(入力ステップの削減)
購入直前の離脱原因として多いのが「入力の面倒さ」です。フォームの項目を減らし、入力しやすくすることで離脱率を大きく下げることが可能です。
- 不要な情報の入力を省く(例:FAX番号など)
- 郵便番号自動入力・住所補完機能の導入
- エラーメッセージの明確化・リアルタイム表示
- スマホでもストレスなく入力できる設計
購入体験をスムーズにし、“面倒くさい”を感じさせない工夫がCVR向上のカギです。
配送料・手数料の明確化/無料化の検討
購入手続きの途中で突然現れる追加料金は、ユーザーに強い不信感を与えます。
- 商品ページであらかじめ送料・手数料を明示
- 一定額以上の購入で送料無料とする
- 決済手数料を明記、または無料化
「後出し料金」を避けることで、購入前後のギャップを減らし、離脱を抑えられます。
ゲスト購入の導入
会員登録が必須だと、“今すぐ買いたい”ユーザーの離脱を招きます。一時的な購入ニーズに応えるため、ゲスト購入機能は非常に有効です。
- メールアドレスと配送情報だけで購入可能に
- 購入完了後にアカウント作成を案内
ゲスト購入を用意することで、初回購入のハードルを下げ、リピーターへの橋渡しがスムーズになります。
カゴ落ちメール(リマインドメール)の活用
ユーザーがカートに商品を入れたまま離脱した場合、一定時間後にリマインドメールを送ることで購入を促進できます。
- カゴ落ちから1〜24時間以内の配信が効果的
- 商品画像・名前・価格を明記し、購入ページへ直リンク
- 限定クーポンや在庫残りの案内も有効
カゴ落ちメールは、もっとも費用対効果の高いリカバリー施策のひとつです。
パーソナライズされたポップアップや割引の提供
離脱しそうなユーザーに対し、行動履歴に応じたポップアップやクーポンを表示することで、コンバージョンを後押しできます。
- 離脱時の「◯%OFFクーポン」提示
- 特定商品への再訪時に「前回のカートに商品があります」表示
- ログイン済みユーザーに向けたリマインド表示
適切なタイミングと内容で表示することで、ユーザーとのエンゲージメントを強化できます。
UI/UXの改善(モバイル対応・決済スムーズ化)
特にスマートフォン経由のユーザーが多い現在、モバイル最適化はカゴ落ち対策の基本中の基本です。
- 決済ボタンの大きさ・色・配置の見直し
- スマホでのレイアウト崩れ防止
- 各ステップが一目で分かる構造にする
- Apple Pay/Google Payなどスムーズな決済手段の導入
“使いやすさ”は購入率を左右する大きな要素。サイト設計を「お客様目線」で見直すことが、CVR向上の近道です。
カゴ落ち対策ツール・サービスの活用

カゴ落ちは、感覚や勘だけでは対処しきれません。「どこで」「なぜ」ユーザーが離脱しているのかを可視化し、適切なアプローチを取るには、専用ツールやサービスの活用が非常に効果的です。ここでは、カゴ落ち防止に役立つ代表的なツールやその活用法を紹介します。
カゴ落ちメール配信ツール(Klaviyo、Recustomerなど)
カゴ落ちユーザーに対し、自動でリマインドメールを送信できるツールは、カゴ落ち対策の基本施策のひとつです。
主な機能とメリット
- カート放棄から○時間後に自動でメール配信
- 商品情報や金額、再購入リンクを自動挿入
- クーポンや割引コードも組み合わせて送信可能
- セグメント別に内容を最適化
代表的なツール
“忘れていただけ”なユーザーを呼び戻し、売上を回収できる施策として非常に有効です。
ヒートマップ・セッションリプレイでの原因分析
ユーザーの離脱理由を感覚で判断せず、実際の動きを可視化して把握できるのがヒートマップツールやセッションリプレイツールです。
分析できること
- どこでスクロールが止まったか(ヒートマップ)
- クリック・タップが集中している場所
- フォームでどの項目が離脱の原因になっているか
- ユーザーがどのタイミングでページから離れたか(録画機能)
代表的なツール
データに基づいた改善点を特定できるため、UI/UXの具体的な見直しに直結します。
A/Bテストツールの活用
複数の改善案を試しながら、どれが最も効果的かを数値で比較できるのがA/Bテストツールです。特に、ボタン文言や色、バナー表示方法、クーポン表示のタイミングなど、ちょっとした変更でもCVRが大きく変わることがあります。
活用例
- 「今すぐ購入」vs「◯%OFFで購入する」などの文言比較
- CTAボタンの位置・色・サイズの違いをテスト
- クーポン表示タイミングの変更(離脱時 vs 訪問30秒後)
代表的なツール
定量的な検証を重ねることで、「効果がある施策」に集中でき、カゴ落ち対策をより効率的に進められます。
成功事例|カゴ落ち対策で成果を出した企業の例

カゴ落ち対策は、正しい施策を適切に実行すれば、明確な成果として数字に表れます。ここでは、実際にCVR(コンバージョン率)の改善につながった企業の事例を3つ紹介します。どのような対策が功を奏したのか、改善前後の比較も交えて見ていきましょう。
1. 改善前後のCVR比較:アパレルECサイトの例
課題
カート追加まではスムーズだが、購入完了率が低く、特にスマートフォンからの離脱が多い。
対策内容
- ゲスト購入機能を導入
- 配送条件を商品ページに明示
- カゴ落ちユーザー向けにクーポン付きリマインドメールを配信
結果
- 改善前のCVR:1.4%
- 改善後のCVR:2.6%
→ 約1.8倍の改善に成功!
特にスマホからの購入完了率が大幅に改善され、広告費の効率も上がった。
2. ECツール導入で離脱率改善:生活雑貨ECのケース
課題
フォーム離脱率が高く、購入完了までの導線でユーザーが迷いやすかった。
導入ツールと施策
- ヒートマップツール(Hotjar)でフォームの離脱ポイントを可視化
- 入力項目の削減とリアルタイムエラーメッセージを実装
- ABテストでCTAボタンの文言と色を最適化
結果
- フォーム離脱率:38% → 21%へ改善
- CVR:1.8% → 3.2%に上昇
ユーザー視点のUI改善がCVR向上に直結した好例であり、社内のデータ活用にもつながった。
3. Recustomerを活用したカゴ落ち防止事例
業種: 化粧品ECサイト
導入サービス: Recustomer 配送追跡・返品・自宅で試着
取り組み内容
- 「Recustomer 返品・キャンセル」導入により返品・交換のしやすさを明確化
- 配送状況を可視化できる「Recustomer 配送追跡」をメールに自動反映
- 離脱ユーザーに対してカゴ落ちメールを配信し、再購入を促進
成果
- 購入直前の離脱率が約15%改善
- カゴ落ちメール経由の再購入率が平均8.4%
- 顧客満足度アンケートで「購入のしやすさ」に関する満足度が上昇
Recustomerの導入によって、購入前後の不安が軽減され、顧客体験の向上と売上回収を両立することができた好事例です。

まとめ

カゴ落ちは、ECサイト運営における「あと一歩」の取りこぼしです。しかし、原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで、確実に改善できる領域でもあります。
購入フォームの見直しや送料表示の工夫、カゴ落ちメールの活用、UI/UXの最適化といった取り組みを通じて、コンバージョン率を高め、売上の最大化と顧客満足度の向上を同時に実現することが可能です。
まずは自社のカゴ落ち状況を把握し、ユーザー目線でサイトを見直すことから始めましょう。それが、ECの成長に直結する第一歩です。